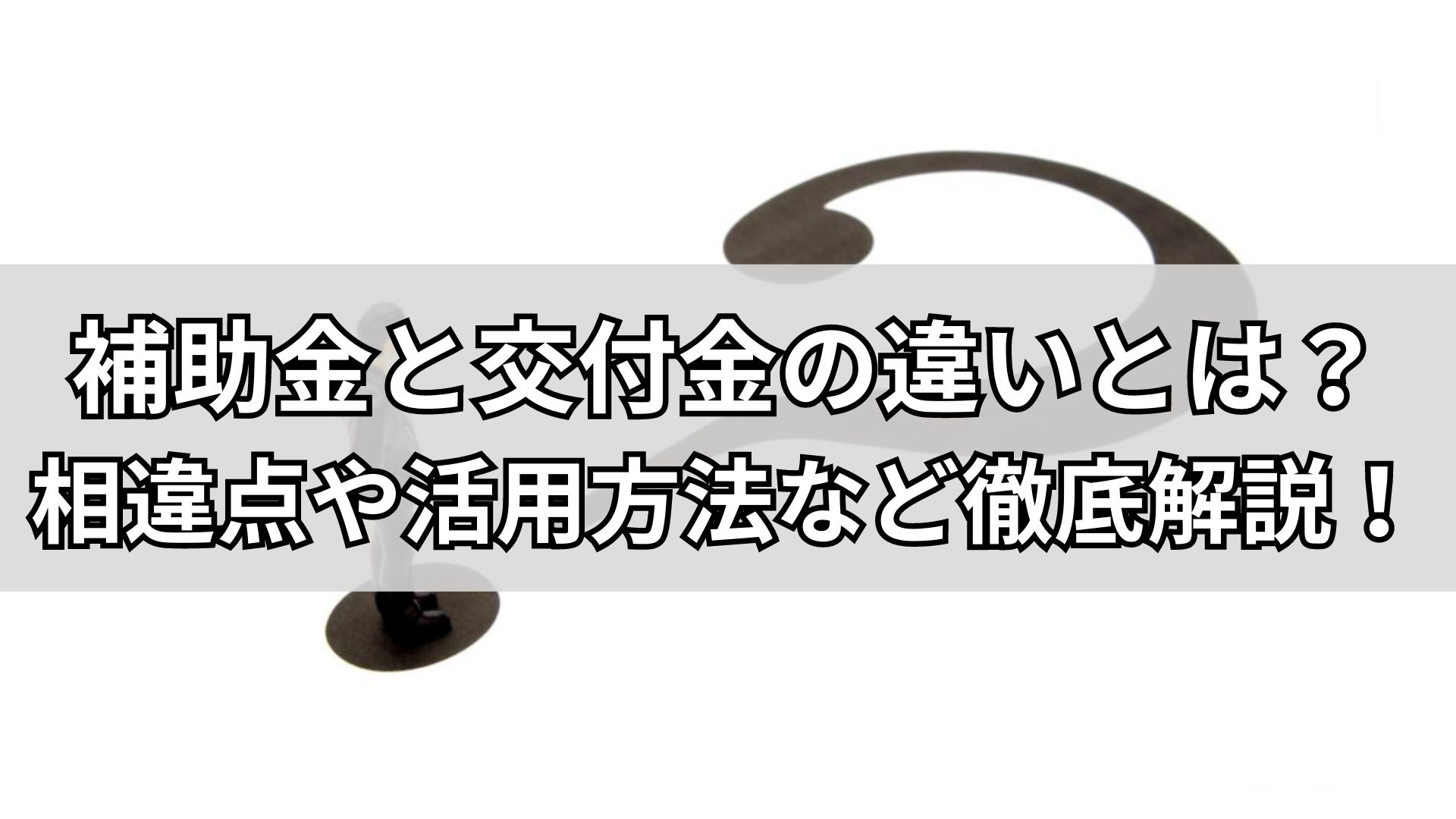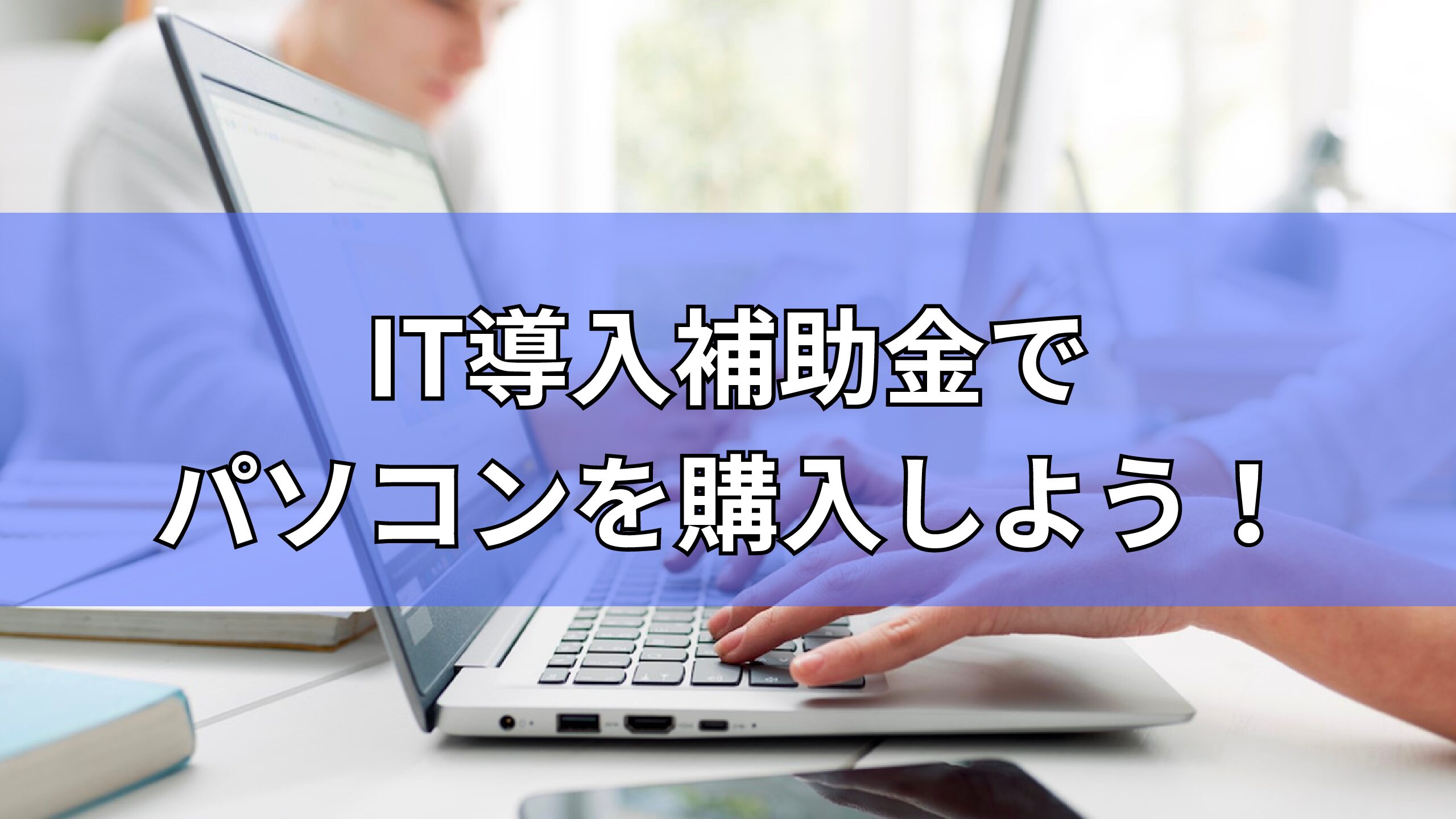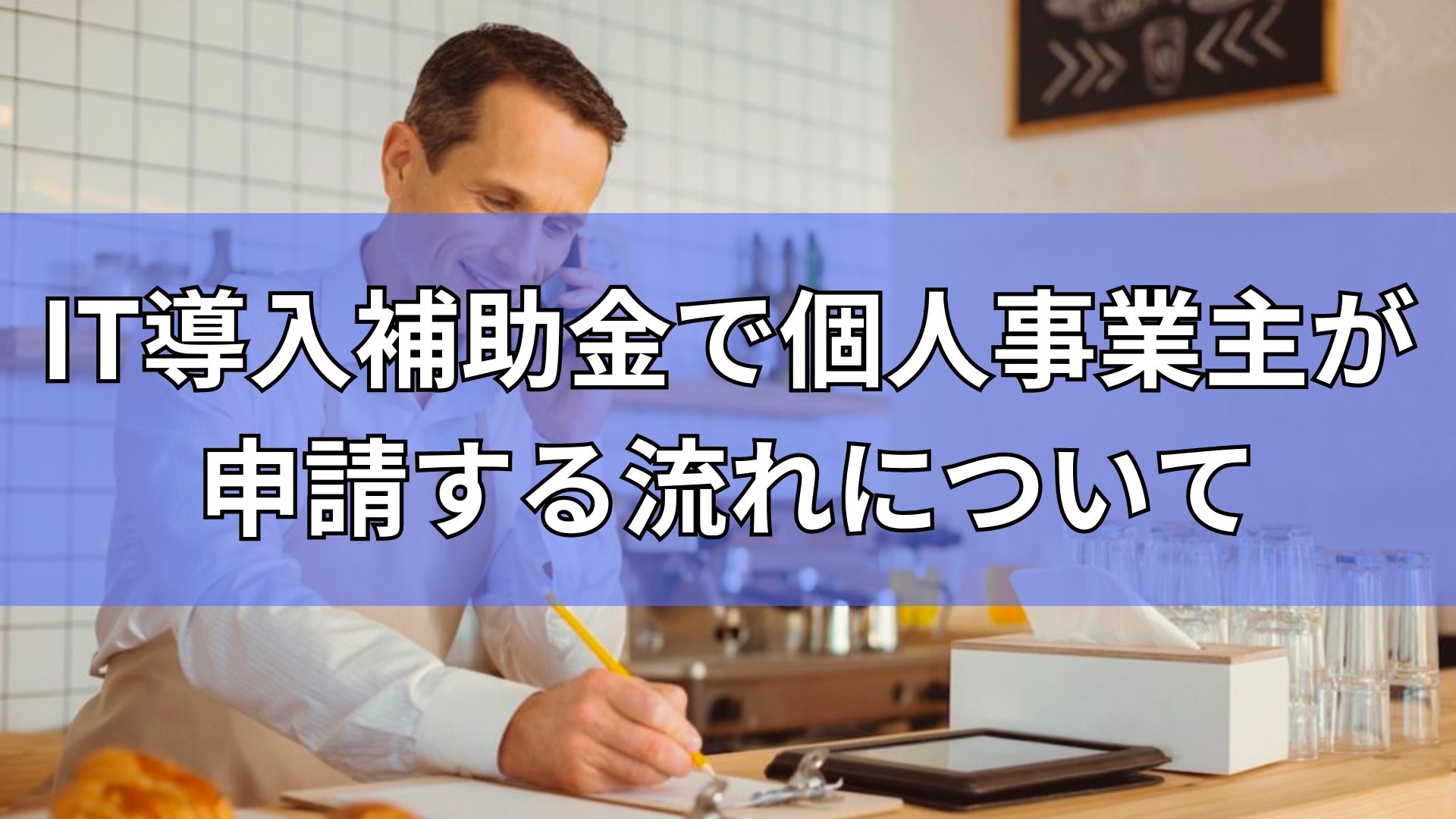- 補助金申請サポート
- ビジネスパートナーシップ
- コラム一覧
- 補助金検索
- 会社概要
-
営業時間 10:00~18:00

TOP
コラム一覧
コラム詳細
【令和5年度最新版】事業承継・引き継ぎ補助金とは?公募要領・申請手続きを徹底解説!
補助金

事業承継・引き継ぎ補助金は令和5年度も引き続き申請受付が開始される予定です。事業承継についてお悩みの事業者様はぜひ活用について検討してみてください。
今回は、事業承継・引き継ぎ補助金の活用を検討している事業者向けに、概要から対象となる要件、押さえておきたいポイントなどを紹介します。
初めて利用を検討されている事業者向けの内容となっているので、「事業承継・引き継ぎ補助金はどのような内容になっているの?」と疑問を持たれている方はぜひ参考にしてみてください。
事業承継・引き継ぎ補助金とは?

事業承継・引き継ぎ補助金とは、事業再編や事業統合を含む事業承継を契機として、中小企業や小規模事業者に対してその取り組みの一部を支援するために創設された補助制度です。
事業承継は中小企業の存続にとって重要な課題の一つとなります。日本においては後継者不足などが大きな問題となっており、やむを得ず廃業するケースも少なくありません。
こういった問題を解決するため、中小企業庁は補助金を活用して積極的な支援を行っています。
事業承継・引き継ぎ補助金の概要
事業承継・引き継ぎ補助金についての概要を下記の表に簡単にまとめました。大きく分けると申請類型は3つの種類があり、それぞれ対象者や補助率、補助額なども変わりますので参考にしてみてください。
| 申請類型 | 補助対象 | 補助率 | 補助上限 |
| 経営革新 | 経営資源引継ぎ型創業や事業承継(親族内承継実施予定者を含む)、M&Aを過去数年以内に行った事業者、または補助事業期間中に行う予定の事業者が対象 | 1/2・2/3 | 600万円 |
| 1/2 | 600万円(賃上げ要件を満たすと800万円まで引き上げ) | ||
| 専門家活用 | 補助事業期間に経営資源を譲り渡す、または譲り受ける人 | 1/2・2/3 | 600万円(M&A未成約の場合は300万円まで) |
| 廃業・再チャレンジ | 事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業等を行う事業者 | 1/2・2/3 | 150万円 |
事業承継・引き継ぎ補助金の申請類型の詳細

事業承継・引き継ぎ補助金には、「経営革新」「専門家活用」「廃業・再チャレンジ」の3つの申請類型があります。
ここではより詳細な内容を紹介するので、活用を検討している事業者は参考にしてみてください。
経営革新
経営革新は、承継後の取り組みにかかる費用を補助するための申請類型です。対象経費となるものには「店舗等借入費」や「設備費」などがあり、ものづくり補助金と比べても幅広い経費対象となるのが特徴です。
なお、経営革新はさらに下記3つのタイプに分かれていますので、それぞれの違いついてもチェックしておきましょう。
1. 創業支援型
創業支援型は、他の事業者の設備や従業員、顧客等を引き継いで創業したケースが対象です。また、創業支援型は下記の要件を満たす必要があります。
・創業を契機として引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む
・産業競争力強化方にもとづく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識があること
2. 経営者交代型
経営者交代型は、簡単に説明すると親族や従業員等、経営者が交代するケースが対象です。経営者交代型は令和4年度第2次補正予算において後継者候補の承継前の取り組みも支援の対象となり、従来よりも使いやすくなっています。
また、経営者交代型は下記2つの要件すべてを満たす必要があります。
・親族内承継や従業員承継等の事業承継
・産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること。
3. M&A型
M&A型はその名の通り、M&Aにより引き継ぐケースです。例えば企業が同業他社等に経営資源を引き継ぎ、事業再編や事業統合をするようなケースが対象となります。
また、M&A型は下記2つの要件をすべて満たす必要があります。
・事業再編・事業統合等のM&Aであること
・産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること
専門家活用
専門家活用事業は、事業を引き継ぐ際にかかる費用の一部を支援してもらえるものです。事業を引き継ぐ際にはさまざまな手続きが必要となり、M&A仲介会社などに依頼するのが一般的となります。
依頼する際には手数料が発生し、規模によっては負担が大きくなるため、これらを補助金で負担してもらう流れとなります。ただし、「M&A支援機関登録制度」への登録が済んでいる専門家への手数料に限られます。
登録が済んでいない専門家に依頼してしまうと補助金が受け取れなくなってしまうため注意しましょう。
また、専門家活用事業には2つのタイプに分かれており「売り手支援型(I型)」と「買い手支援型(Ⅱ型)があります。
それぞれの内容については下記で紹介するので参考にしてみてください。
1. 売り手支援型(I型)
M&Aによって事業を引き継ぐ際の売り手側を支援するためのものです。売り手支援型を活用するためには、下記の要件を満たす必要があります。
・地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業であり、事業再編等によりこれらが第三者に継承されることが見込まれること
2. 買い手支援型(Ⅱ型)
M&Aによって事業を引き継ぐ際の買い手側を支援するためのものです。買い手支援型を活用するためには、下記2つの要件を満たす必要があります。
・引き継ぎ後にシナジーを生かした経営革新等を行うことが見込まれること
・引き継ぎ後に地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること
廃業・再チャレンジ
廃業・再チャレンジとは、その名の通り廃業や再チャレンジを行う中小企業者等を支援するための事業です。
廃業・再チャレンジ事業には経営革新事業・専門家活用事業と合わせて申請を行う「併用申請」と単独で申請する「再チャレンジ申請」があります。
申請するには下記の要件を満たす必要があるため、参考にしてみてください。
・事業承継後M&A後の新たな取り組み
・M&Aによって他者から事業を譲り受ける(全部譲渡・一部譲渡含む)
・M&Aによって他者に事業を譲り渡す(全部譲渡・一部譲渡含む)
・2020年以降に売り手としてM&Aへの着手し、6か月以上取り組んでいること+廃業後に再チャレンジ
事業承継・引き継ぎ補助金の対象経費

事業承継・引き継ぎ補助金の対象経費は、申請類型によっても異なります。ここではどのような経費が対象になるのか具体的に紹介するので、対象経費について知りたい人は参考にしてみてください。
経営革新の対象経費
経営革新では、大きく分けると事業費と廃業費が対象経費として含まれています。下記では詳細な内容について紹介しているので、経営革新の対象経費を確認したい方は参考にしてみてください。
事業費
・人件費
・店舗などの借入費
・設備費
・原材料費
・産業財産権など関連経費
・謝金
・旅費
・マーケティング調査費
・広報費
・会場借料費
・外注費
・委託費
廃業費
・廃業登記費
・在庫廃棄費
・解体費
・原状回復費
・リースの解約費
・移転・移設費用(ただし、Ⅱ型は不可)
専門家活用の対象経費
専門家活用では、謝金や旅費、廃業支援費等が対象経費として含まれています。具体的には下記に記載されている内容が対象となりますので参考にしてみてください。
事業費
・謝金
・旅費
・外注費
・委託費
・システム利用料
・保険料
廃業費
・廃業支援費
・在庫廃棄費
・廃業登記費
・解体費
・原状回復費
・リースの解約費
・移転・移設費用
廃業・再チャレンジの対象経費
廃業・再チャレンジ事業では、主に廃業費が対象経費として含まれます。具体的には下記に記載されている内容が対象となるため、参考にしてみてください。
・廃業支援費
・在庫廃棄費
・解体費
・原状回復費
・リースの解約費
・移転・移設費用
事業承継・引き継ぎ補助金のスケジュール

事業承継・引き継ぎ補助金は令和5年度も引き続き実施されます。すでに申請受付が開始されていますが、まだ締め切られてはいないため、活用を検討している事業者は早めの申請を検討してください。
令和5年度の事業承継・引き継ぎ補助金のスケジュールは下記のように進められる予定です。
1. 公募要領公開(3月14日)
2. 申請受付開始(3月20日〜5月12日まで)
3. 交付決定(6月中〜下旬ごろ)
4. 補助事業完了日(2024年1月22日)
5. 実績報告(2024年2月10日)
6. 確定検査
7. 補助金交付請求
8. 補助金交付(2月中旬〜)
上記が2023年度の5次公募申請スケジュールとなっています。あくまでも予定となっておりますので、スケジュールは変更となる可能性もあります。
そのため、活用を検討されている事業者は、ギリギリのスケジュールとならないよう早めに準備しておきましょう。
事業承継・引き継ぎ補助金の活用に向けた相談先は?

事業承継・引き継ぎ補助金に限らずですが、補助金の申請は複雑であり、不備等があると採択される確率が下がってしまいます。
専門的な知識がある場合を除き難易度は高いため、できれば申請前に専門機関への相談をおすすめします。
補助金オフィスでは、事業承継・引き継ぎ補助金を検討されている事業者向けに、申請代行サービスを実施しています。
申請資料の作成等、トータルサポートを実施しておりますので、補助金についてよくわからないとお悩みの事業者様はぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせはこちらから:https://hojokin-office.essencimo.co.jp/contact/
まとめ
今回は事業承継・引き継ぎ補助金の概要についてまとめました。事業の引き継ぎには後継者の問題もありますが、M&Aなどを活用する場合にはコストもかかります。
負担は大きなものとなりますので、少しでも軽減させるためには補助金の活用がおすすめです。
補助金にはさまざまなメリットがありますので、特に事業承継・引き継ぎにお困りの事業者様は活用について検討してみてください。
出典:
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2023/230314shoukei_kobo.html